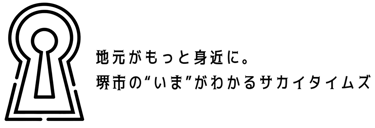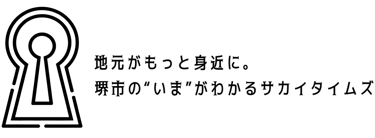堺の歴史をつなぐ「竹内街道」ってなんなん
たまに道ばたに石柱あるやろ?
堺のニュース文化・歴史


堺市内を通る竹内街道ってどんな道?
竹内街道(たけのうちかいどう)は、堺市内でもよく通る道のひとつやで。たとえば、堺駅の周辺から出発して、大浜中町を抜けて、大小路通りを東に進み、大泉緑地の北側を通るルートが竹内街道の一部になっているわ。この道をもっと進んでいったら、松原市に入るんやけど、その境目は国道309号線(松原市三宅中あたり)になるねん。
普段はなんとも思わない道かもしれんけど、実はこの竹内街道、日本最古の官道として1300年以上の歴史があるんやで。まぁ、いまでいう国道や。さらに、日本遺産にも認定されているし、昔から堺と奈良をつなぐ大事な道として使われてきたんや。そんな古い道がいまでも残っているということやわ。
なんで「竹内街道」って「たけのうち街道」って読むん?
そもそも竹内街道は「たけのうちかいどう」って「の」が多いやないか、「たけうち街道ちゃうんかい」って思うやろ。そんな竹内街道の名前の由来は、奈良県葛城市にある「竹内(たけのうち)」という地名からきているんよ。昔の日本では「○○の内」という地名が多かったから、本来は「竹の内」と呼ばれていたんやけど、時代が経つにつれて表記が簡略化されて「竹内」になったんや。でも、発音だけはそのまま残って、今でも「たけのうち街道」と読まれているんやな。
ほかにも「の」が残っている名前は結構あるんやで。たとえば、竹内宿禰(たけのうちのすくね)、源頼朝(みなもとのよりとも)、藤原道長(ふじわらのみちなが)なんかもそうやな。昔は「○○の○○」という形で呼ばれていたものが、表記が変わって「の」だけ発音に残ったんやな。竹内街道もそのパターンやねん。
ちなみに、奈良県葛城市にある竹内神社も「たけのうちじんじゃ」と「の」を入れて読むんやで。竹内街道と同じく、元々の「竹の内」の発音が残っているんやな。
竹内街道は「日本最古の国道」
「官道(かんどう)」というのは、今でいう国道みたいなもので、古代の公的な道路のこと。竹内街道は、推古天皇21年(613年)に「難波(なにわ)から京(飛鳥)に至る大道(おおじ)を置く」という記録が残っている、日本最古の官道なんやわ。
難波は大阪のあたりやけど、「京」は京都ちゃうで。平城京って習ったやろ?そやからこの京は奈良やねん。つまり、そんな頃からあった竹内街道は、今の国道1号線とか国道26号線みたいな道の元祖ってことやな。難波に向かうほうの道はあんまり残っていないんよ。
そして2017年には、この道の歴史的な価値が認められて、竹内街道は「日本遺産」にもなったわ。堺市内の道がこんなに昔からあって、全国的にも貴重な道やってことを知っている堺市民は意外と少ないんちゃうやろか。
竹内街道と堺のつながり
もともと竹内街道は、大阪の難波宮(今の大阪市あたり)から奈良の飛鳥へ続く官道として作られたんや。でも、時代とともに役割が変わってきて、堺とのつながりも深くなっていったわ。
飛鳥時代(7世紀):難波と飛鳥をつなぐ道
竹内街道は、都(飛鳥京)と難波宮を結ぶ重要な道やった。
中世(室町〜戦国時代):堺が発展して竹内街道が大事な物流ルートに
室町時代になると、堺は貿易都市としてとても栄えて、日本一の商業都市のひとつになったんや。
江戸時代以降:堺の大小路が竹内街道の新たな起点に
江戸時代には、堺の大小路が交通の要となって、竹内街道の起点としての認識が強まったわ。
なんで終点(始点)が堺市の大小路なん?
① 交通の要衝としての堺
竹内街道が整備された飛鳥時代(7世紀頃)、当時、大小路のあたりは今よりも海岸に近く、大阪湾からの船と陸の道をつなぐには絶好の場所やったんや。
つまり、海から運ばれてきた物を陸の道に載せ替える拠点として、堺はとても大事な場所やった。大小路は「陸と海の物流が交わる結節点」やったからこそ、竹内街道の起点(または終点)になったんやな。
② 古代の難波(なにわ)とのつながり
当時の都やった飛鳥(奈良)から難波(大阪)へ行く最短ルートとして、竹内街道が整備されたんや。奈良から堺に来て難波に行くのは、右に曲がる感じやな。港もあるし、堺を通るのが一番ええルートやったというわけや。
特に、大小路周辺は交易や物流の拠点として賑わっていて、奈良と大阪(難波)をつなぐルートの中でも、堺の大小路はとても重要な中継点やったってこと。
堺の町の発展と関係
室町時代以降、堺は貿易の町として発展し、「東洋のヴェネツィア」と呼ばれるほど栄えていた。鉄砲や包丁も有名やね。商人の町としての堺は、日本国内だけでなく海外との交易でも中心的な役割を果たしていたんやで。
江戸時代には、大小路は堺の主要な街道(紀州街道や長尾街道)ともつながって、交通の中心地になった。こうして堺の町が発展するにつれて、大小路がずっと街道の拠点として機能し続けてきたんや。現在でいうと、まるでハブ空港みたいな存在やねん。
竹内街道は今もほぼ現存
竹内街道は、大阪府堺市から奈良県葛城市までの約26kmが、今もほぼそのまま残っているわ。昔の道のまま使われているところもあれば、国道166号線や府道30号線と重なっているところもあるんや。
堺市内では、堺駅から大小路通りを東へ進み、大泉緑地の北側を通る道が竹内街道にあたるねん。堺駅から新金岡駅までGoogleマップで歩いたら約1時間15分ほどやけど、ゆっくり歴史散策しながらなら3時間くらいやわ。知らない道を歩いたり走ったりするくらいなら、竹内街道を通ってみるのもええかもしれんね。
堺市民なら知っての通り、この道は単なる歴史の遺産ではなく、今も地元の人が普通に通る道として使われている。でも最近では「歴史街道」として再評価されて、観光資源としての活用も進められているんよ。竹内街道を歩いたら、堺から飛鳥まで続く歴史の流れを実際に感じられるし、1300年以上もこの道が生き続けていることに気づくはずやで。
ようするに竹内街道は、昔からずっと堺の発展とともに歩んできた道。これからも堺の歴史を伝えて、未来へとつながる大切な道として残っていくんちゃうかな。竹内街道は「昔の道」やなくて、今も堺の歴史とまちをつなぐ大事なルートってこと。まぁ、たまには歴史に思いを馳せよか。
※サカイタイムズでは堺市民にわかりやすいよう堺弁で書いています。 堺弁β版について