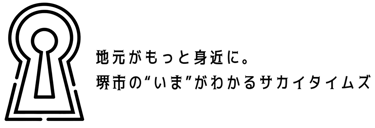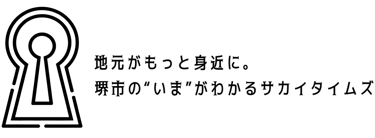(サカイタイムズ調べ)堺の環濠について
そもそも環濠(CANGO)ってなんなん
文化・歴史


1. 環濠ってなんなん?
堺の環濠(かんごう)っちゅうのは、町を守るために掘られたお堀のことやで。昔は戦が多い時代やったから、堺は町の周りに堀をめぐらせて、大名に支配されんようにしとったんや。堺はお城を持たんと自治をやっとったから、環濠が町全体の「城壁」みたいな役割をしとったんやな。
2. 環濠都市が発展した時代
環濠が本格的に作られたんは16世紀ごろや。このころ、堺は南蛮貿易(ポルトガルや明との貿易)が盛んになって、海外との取引がどんどん増えていったんや。さらに、鉄砲が日本に伝わると、堺の職人がその技術を学んで、鉄砲生産でも発展していったんや。
堺の商人らは「会合衆(かいごうしゅう)」っちゅう組織を作って、自分らで町を治めとったんや。町の西側は海(現在の大阪湾)、他の三方を環濠で囲んで、「環濠都市」を築いたんや。環濠の入口になる橋には門をつけて、門番がしっかり見張っとった。こうして、よそもんが簡単に入られへんようにして、戦国時代の大名に支配されんようにしとったんやな。
ポルトガル人の宣教師ガスパル・ビレラも堺を訪れて、「日本のベニスのごとし(ベニスみたいな自治都市や)」と本国へ報告しとるで。当時の堺は、経済力・技術力・自治の面で特別な町やったっちゅうことやな。
3. 鉄砲生産でさらに発展
1543年にポルトガル人が種子島に鉄砲を伝えたんやけど、堺の商人らはすぐにその技術を学びに行ったんや。堺にはもともと優れた鍛冶職人がぎょうさんおったから、鉄砲生産の主要な拠点になったんやで。
戦国時代の大名にとって、鉄砲は戦の勝敗を決める大事な武器やった。せやから、堺の鉄砲はよう売れたし、町もさらに発展していったんや。ほんで堺で作られた鉄砲は、その精度の高さで知られるようになって、「堺鉄砲」として広まったんや。
4. 堺には大名も藩もなかったんか?
戦国時代の前半までは、堺は大名に支配されんと、商人らが自分らで町を治めとったんや。でも、1570年代になると、織田信長が堺を支配下に置いて税を取るようになったんや。
このとき、信長は堺の会合衆に「矢銭(やせん)」っちゅう軍事資金を出せと要求したんや。矢銭っちゅうのは、戦国時代に戦の費用として特別に集められた金のことで、大名にとっては大事な財源やった。信長は2万貫(今の価値で約20億円~40億円)を出せと迫って、払わんかったら町を攻めるぞと圧力をかけたっちゅう話が残っとる。
その後、豊臣秀吉の時代になっても堺は特別な町として扱われて、ある程度の自治は認められとったけど、もう完全な独立都市とは言えんようになったんやな。江戸時代になると、堺は幕府の直轄地(天領)になって、大名のおるような城下町とは違う形で幕府の管理を受けるようになったんや。
5. 環濠があっても、大名には攻められへんかったんか?
環濠は町を守るために作られとったけど、大名の大軍を完全に防ぐことはできんかった。1576年には、織田信長が堺を支配するために兵を送り込んできたんや。環濠は多少の抑止力にはなったけど、結局は信長には勝てんかったんやな。
戦国時代の終わりごろには、環濠の防衛機能もほとんど意味をなさへんようになって、町としての機能のほうが重視されるようになったんや。
6. 信長以降の堺はどうなったんや?
織田信長の時代(1570年代)
→ 高い税を課され、自治がだんだん制限されていった。豊臣秀吉の時代(1583年〜)
→ 環濠の防御の役割はほぼなくなって、埋められはじめた。江戸時代(1603年〜)
→ 幕府の直轄地になって、環濠は都市開発のためにどんどん埋められていった。
7. 環濠がちゃんと機能しとったんは、いつまでや?
環濠が自治を守るためにしっかり機能してたんは、信長が来るまで(1570年代以前)やな。信長が堺を支配下に置いたあとは、環濠の意味も薄れていったし、秀吉の時代には埋め立ても進んだんや。
8. 今でも環濠は残っとるんか?
大部分は埋められてしもたけど、一部は今も残っとるで。
土居川(どいがわ) … 環濠の名残として残ってる川(約2kmな)
旧堺環濠エリア(大小路周辺) … 町のつくりや地形に環濠の跡が残ってるわ
いまでも、これらの場所に行ったら、昔の堺の環濠都市の雰囲気を感じることができるで。歴史を知ることで、堺がどんな町やったんかがよう分かるっちゅうことやな。堺を巡る探偵×推理ファンタジー『謎解けば堺』に関係するかどうかは知らんけど。
※サカイタイムズでは堺市民にわかりやすいように堺弁で書いています。堺弁β版について