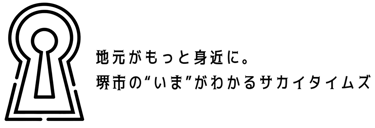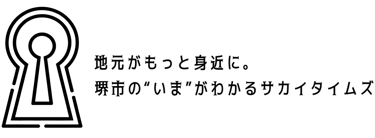堺でまた埴輪(はにわ)発見
御廟表塚古墳(ごびょうおもてづかこふん)や
堺のニュース文化・歴史


登れる古墳として知られる御廟表塚古墳(ごびょうおもてづかこふん)で、埴輪列が発見された。発見された埴輪は合計9基やで。
堺市では、国指定史跡・百舌鳥古墳群の一つである御廟表塚古墳の保存と公開活用のため、令和6年10月から史跡整備工事を進めていた。その際の令和7年2月10日(月)に後円部北側の平坦面で埴輪列が確認されたんや。埴輪列は、古墳の構造を知るうえで重要な要素のひとつであり、今後の整備工事では、遺構が適切に保護されるよう文化庁と協議のうえ対応していくとのこと。
確認された埴輪列
後円部北側で排水溝設置のため溝状に掘削した箇所において、幅約2mの範囲で埴輪7基を確認
埴輪列の西側で埴輪を据えた痕跡を2基分確認
御廟表塚古墳について
御廟表塚古墳は、大阪府堺市にある古墳で、百舌鳥古墳群を構成する44基の古墳のひとつ。世界文化遺産に登録されている23基には含まれていない。所在地は大阪府堺市北区中百舌鳥町4丁で、南海高野線「百舌鳥駅」から徒歩5分の場所にある。別名「八幡塚」とも呼ばれていた。
形は墳丘の西側に前方部を持つ帆立貝形古墳(前方後円墳)で、全長84.8m、高さ8mの規模を有し、百舌鳥古墳群の中では11番目に大きい古墳。耕地開発や宅地開発により、周濠の大半が埋められ、前方部が失われている。現在の史跡指定地は、後円部および北東隅に残された周濠の一部のみ。
5世紀後半に築造され、過去の発掘調査では後円部が2段に築かれ、平坦面に埴輪列が巡っていたことが確認されている。平成20年度(2008年度)の地中レーダー探査では、後円部中央に埋葬施設が存在する可能性が指摘され、平成23年度(2011年度)の発掘調査では、後円部が2段築成であり、テラス上に埴輪列が並ぶことが確認された。2014年3月18日に国の史跡に指定された。
埴輪列確認の経緯
2月10日(月)午前10時30分頃
墳丘に設置する排水溝の工事中、文化財課職員が立会調査を実施
掘削された壁面で埴輪列を確認し、文化庁に報告
2月12日(水)
埴輪列の現況調査および記録作成を実施
今後の対応
文化庁と協議を進めるとともに、堺市百舌鳥古墳群等史跡保存整備委員会の意見も踏まえ、遺構の保護を実施する予定。
※サカイタイムズでは堺市民にわかりやすいよう堺弁で書いています。堺弁β版について