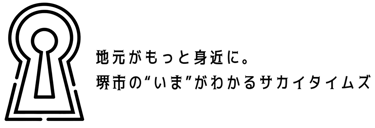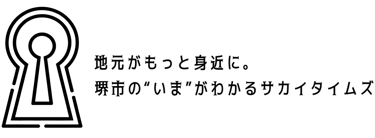「んっ?地元では13号線ですけど?」 府道30号の不思議な名前の由来
ほんまは大阪府道30号線でも、なんでみんな「13号線」って呼んでるんやろ?いろんな説を調べてみたで
文化・歴史


13号線が30号線って?
堺の人やったら「13号線」って聞いたらすぐピンとくると思うねんけど、地図や標識をよう見たら「大阪府道30号線」って書いてあるんよね。ほな、なんで昔から「13号線」って呼ばれてるんやろ?って思って、いろいろ調べてみたんよ。
そしたら、はっきりこれやって決まった理由はないねんけど、それなりにもっともらしい説がいくつかあんねん。どれも地元の人がそう呼び始めた背景があって、いまも生活の中に残ってるんやろね。今回は、サカイタイムズが選んだ有力な3つの説と、ちょっと弱そうな説、ほんで「13号線」って呼び名が堺でどんなふうに生き続けてきたんかを紹介していくで。
・サカイタイムズが考える有力な3つの説
【1】昔ほんまに「府道十三号線」やったことがある説
昭和11年(1936年)9月29日に出された内務省告示第516号には、
「十三号線(泉北郡鳳町ニ於テ分岐)、泉南郡土生郷村、北中通村、熊取村、大土村和歌山県界」
「十三号線(堺市ニ於テ分岐)、岸和田市、泉佐野市、熊取町、泉佐野市和歌山県界」
って書かれててな、当時ほんまに「十三号線」っていう府道が存在しとったことがわかるんよ。
その道の名前はそのあとに道路の整理で一度なくなったらしいんやけど、いまの府道大阪和泉泉南線(大阪府道30号線)の一部の区間は、その「十三号線」とルートがかぶってるみたいやねん。せやから、むかしの呼び名が地元の人にずっと使われ続けてるんやろなって思われてるんよ。
【2】道幅13間の計画名がそのまま残った説
「間(けん)」っていうのは、昔の単位で1間が約1.8メートルぐらいやねん。13間やったら23.4メートルぐらいになるんよ。この道の一部は大正時代からあったみたいやし、戦前の時点で「13間道路」って呼ばれてたっていう話も残ってるんよね。
ほんで、1954年に堺の中心部で幅13間に広げる計画が正式に決まって、それが「13間道路」って呼ばれるようになっていって、そのうち「13号線」って言いかえられていったんちゃうかって言われてるねん。
【3】都市計画の「阿部野堺線」が元になった説
大阪府が1926年に計画した「十大放射路線」っていうんがあってな、その中に「阿部野堺線」っていう道があるんよ。この道が13間幅で作られて、1931年に完成したらしいねん。松虫交差点から北花田口交差点までの区間は、今の府道30号線と重なってるねんて。
この道も「13間道路」って呼ばれてたみたいやし、そこから今の「13号線」っていう呼び方につながっていったんやないかって言われてるんよ。
ほかにもあるけど、ちょっと弱い説も
たとえば「国道26号の半分の幅やから13号線」っていう説とか、「30号を逆さに読んだら13になるから」っていうのとかもあるんやけどな、これはちょっとこじつけっぽいよなぁ。
あとは「大阪府が昭和35年に考えた環状線の13番目の道やったから」って説もあるんやけど、実際の計画書にそんな記載はないらしいねん。せやから、このへんの説は信ぴょう性があんまり高くないみたいやね。
地元に定着していった背景といま
いろんな説があるけど、「13号線」って呼び名は、いつの間にか堺のまちにしっかり根づいてしもたんやろね。「13号線バッティングセンター」っていう名前のお店もあったくらいやし、行政で働いてる人でも、家では「13号線」、職場では「30号線」って呼び分けてるっていう話もあるんよ。
行政資料から通称が消えつつある現状
堺市が出してる資料の中には、府道大阪和泉泉南線(13号線)って書いてある例がいまでもあるんやけど、本来の正式名称は府道大阪和泉泉南線(30号線)。せやけど「13号線」っていう呼び名が地元でよう使われてきたから、資料の中にも併記されとったわけやね。
でも、ここ最近ではその「13号線」って表記も堺市の資料でもだんだん消されつつあるねん。2025年1月に改訂された堺市の津波警戒マップでは、ついに「13号線」の記載が消えてしもたわ。
堺はむかし「自治都市」って言われてて、商人たちが自分らでまちを治めてた歴史があるし、一時期は大阪府とは別に「堺県」やった。そういう背景があるからか、なんでも大阪府の言うことにそのまま従うって風土やないんかもしれへんな。せやけど、そんな堺やからこそ、住民に愛されてきた呼び名が消えていくんは、なんやちょっと寂しいなぁって感じる人も多いんちゃうかな。知らんけど。
※サカイタイムズでは堺市民にわかりやすいよう堺弁で書いています。 堺弁β版について