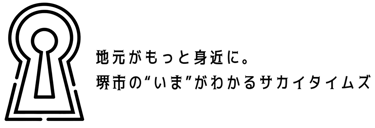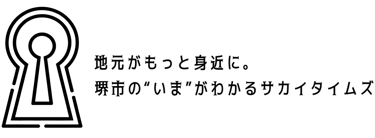堺市がLiD/APD調査研究を実施
誰のためなんやろ?協力者募集ともちゃうみたいやねん
政治・行政


堺市がLiD/APDの調査研究を発表
堺市が「聞き取り困難症・聴覚情報処理障害」(LiD/APD)の研究事業を始めるって発表してん。ただし、対象はごく一部の子どもたちだけ。その子らも治療や新しい支援が受けられるわけやなく、研究のために協力してデータを取らせてもらう感じやねん。
市の発表では「調査・研究を実施します」となってるけど、実態はただの協力者募集と変わらへん内容。市民向けの新しい発表や還元策も今のところ特にないみたいやし、こういう“ようわからん地味な事業”にも税金が使われてるんやってこと、知っといてもええかなと思って。まぁ今後どうなるんか、市民としては静かに注目しとこか。
どんな事業なん?
堺市は大阪公立大学、補聴援助機器メーカー(スイス本社の外資系・ソノヴァ・ジャパン)と組んで、「聞き取り困難症・聴覚情報処理障害」(LiD/APD)の調査・研究を始めるとのこと。LiD/APDは、音としては聞こえてるのに会話が聞き取りにくかったり、雑音があると何を言われてるのか分からなくなったりする症状で、子どもや保護者も気づきにくいことが多いねん。
この研究の対象は、堺市内に住む小・中学生のうち、専門医による診断で「ロジャー」という補聴援助システムを使った方がええとされた子どもたち、20名ほど。実施期間は3年間の予定やわ。今回使われるロジャーは、外資系のソノヴァ・ジャパンが開発・販売してる補聴援助システムやねん。大学とメーカーが組むのはよくある話やけど、こうした外資系メーカーの製品を使った研究に、自治体である堺市が加わっている理由は分かりにくいところやわ。
どんな流れなん?
まず、専門医が診断して「ロジャー」の使用を勧められたら、堺市や大学から説明があるねん。そのあと、対象になった子どもと家族は説明会でロジャーの使い方を教えてもらい、相談先や連絡先も伝えられるみたいや。ほんで実際の生活や学校でロジャーを使ってもらって、困ったことがあれば市や学校、大学の先生に相談できる体制にはなってる。
でも、これはあくまで「研究への協力」やから、たとえば本人や家族が「このまま機器を使い続けたい」と思っても、研究期間が終われば返却になる可能性もあるし、新しい支援が受けられるとも限らへん。あくまでも研究目的やから、困っている市民に幅広く機器を貸与する施策というわけでもないところがポイントやねん。
学校や家庭でどう使うん?
ロジャーは、小型の送信機と受信機でできてて、先生がマイクで話した声が直接子どもの耳に届く仕組みになってるんよ。たとえば教室がざわついてるときでも先生の声だけはっきり聞こえたり、家庭でも親の声が届きやすくなったりするねん。実際には機器の使い方や準備、学校の協力も必要になるけど、今回は「効果を調べる研究」やから、そうした実際の使い方についてもいろいろ記録していくことになる。
調査・研究で何が分かるん?
この事業で集めたデータは、「ロジャー」を使うことで本当に聞き取りが良くなるのか、学習や日常生活にどんな変化があるかを検証するために使われるねん。ただ、現時点では「調査・研究に協力した本人や家族に結果がどうフィードバックされるのか」「市全体で今後どんな支援に生かされるのか」については、具体的な説明や約束はないんよ。いまいちよくわからん事業やけど、市民に還元されるなにかに変わるかもしれんから市民はこれからの動きを見ていこ。


※サカイタイムズでは堺市民にわかりやすいよう堺弁で書いています。 堺弁β版について