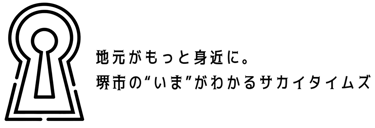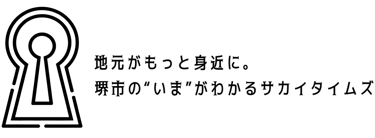【謎付き】仁徳天皇陵古墳の副葬品を新発見 國學院大學が発表
堺で153年ぶりに初公開される金銅装刀子など副葬品の流れを検証しといたで
文化・歴史堺のニュース


國學院大學が新発見を発表
國學院大學では、かねて内川隆志・文学部教授を中心に、幕末・明治の好古家についての研究を進めてたんや。そしたら著名な好古家である柏木貨一郎・益田孝旧蔵資料を入手し、本学博物館に収蔵することになった。特に、その中に含まれていた「仁徳帝陵」出土とされる資料について、大阪府堺市および日鉄テクノロジー株式会社との共同調査を行ったら「仁徳天皇陵古墳(大仙陵古墳)」の副葬品として良いものと確認されてん。
堺市によると副葬品の金銅装刀子(こんどうそうとうす)は、金メッキした銅板で飾られた鞘に鉄製の刃が納められたもんやねん。7月19日から堺市博物館で一般公開される予定やで。
ここまでが堺市と大学発表の一次情報。ここから少し謎解きしよか。
【報じない自由】
大手メディアも大学の発表を元に写真を付け「新発見」という論調で報じているけど、報じていない部分も多いねん。実は旧蔵資料に名前があった「益田孝」は元三井物産の創業者。せやけど、ほとんどのメディアは益田孝についてほとんど触れていないか、副葬品の流れが曖昧。今回の場合、天皇陵副葬品というセンシティブな文化財が“旧財閥関係者のコレクション”になっていたという事実は、世間には知らされていないことになるねん。
謎1.一次情報には「柏木貨一郎・益田孝旧蔵資料」って名前が2つあるやん
謎2.大手メディアは誰が副葬品を持っていたか名前書いてないところ多いな
謎3.旧三井物産の創業者のとこにあったけど古墳からの盗掘品じゃないのか
各社6月19日付 「柏木貨一郎・益田孝旧蔵資料」についての記述まとめ
【共同通信】
「国学院大が入手した新発見の史料で、共同で研究していた」とだけ記載。(※旧蔵主や伝来経路に全く触れていない)
【毎日新聞】
「明治時代の古物収集家、柏木貨一郎(1841~98年)の遺品から発見された」と記載。包み紙に柏木の印が押されていたとするが、益田孝や美術商には言及なし。
【NHK】
「国学院大学博物館が去年6月、古美術商から小刀や甲冑の破片を入手しました」と記載。包み紙には図面を作成した人物の押印がある、とだけ触れ、柏木貨一郎の名は説明文脈にのみ登場。益田孝には言及なし。
【読売新聞】
「国学院大学博物館(東京)が昨年6月に購入した旧三井物産初代社長・益田孝のコレクションにあった」と明記。柏木貨一郎は「調査に加わった絵師」とし、「柏木の没後に益田が受け継いだ可能性がある」と説明。
【朝日新聞】
「同博物館が美術商から買った」と明記。「柏木が副葬品の一部を手元に残していたとみている」と説明し、包み紙に柏木の朱印があることに触れる。益田孝については言及なし。
【日経新聞】
包み紙には「栢」の朱印が押されており、これは古美術収集家・建築家の柏木貨一郎が用いたものとみられる。柏木の没後は親交のあった益田孝(益田鈍翁)の手に渡った。益田孝は三井物産初代社長などを務め、茶人としても知られ、多くの美術品を柏木家から受け継いだ。国学院大学博物館が昨年、益田が収集した様々な考古資料と一括で入手し、調査を進めていた。
益田孝は三井物産初代社長などを務め、中外物価新報(現・日本経済新聞)を創刊した実業家である。
【サカイタイムズの見解】
今回の副葬品の伝来経路について、日経新聞だけが柏木貨一郎→益田孝→美術商→國學院大學博物館と詳しく流れを記載し、益田孝が日経新聞の創業者であることまで紹介していたわ。他紙は柏木の遺品、美術商経由など断片的な説明にとどまっていて、副葬品がどう流れてきたか全体像までは触れてなかった。その他のメディアは財閥に対しての自主規制の可能性が高いわ。
以下、今回見つかった仁徳天皇陵古墳の副葬品(刀子・甲冑片、包紙)が、どうやって堺市博物館で展示されることになったのか、経緯をざっと整理するで。
【副葬品の流れ】
明治5年、仁徳天皇陵古墳(大仙陵古墳)の斜面が崩れて石室が露出
→ 現地調査に柏木貨一郎さん(幕末~明治の好古家)が同行して記録と絵図を残す
→ 一部の副葬品(刀子・甲冑片など)を柏木さんが持ち帰ったとみられる(包紙に柏木さんの印)
→ 柏木さん亡きあと、そのコレクションが実業家・益田孝さん(元三井物産初代社長、茶人)に引き継がれる
→ さらに戦後、益田家のコレクションが美術商の手に渡る
→ 2024年6月、國學院大學博物館が美術商からまとめて購入
→ 包紙や内容を調査し、大阪府堺市・日鉄テクノロジーと一緒に科学分析
→ 2025年6月、國學院大學と堺市が「仁徳天皇陵古墳の副葬品」として正式発表
→ 2025年7月19日から堺市博物館の企画展で初公開予定(いまココ)
こんな感じで、150年近く人の手を渡ってきたもんが、いま堺で「里帰り」展示されるって流れやねん。堺市は地元なんやからサカイタイムズの読者は知っておいてもええんちゃうかな。
文化財保護法の制定と「盗掘」について
最後に盗掘かどうかやけど、明治5年当時はまだ文化財保護法が存在せんかったんよ。文化財保護法は昭和25年(1950年)に制定された法律で、それ以前は発掘された副葬品を個人で持ち帰っても違法にはならへん時代やった。今回見つかった刀子や甲冑片も、現場に立ち会った柏木貨一郎さんが自分で記録して収集したもので、その後、好古家や実業家のコレクション、美術商を経て、最終的に國學院大學博物館に収蔵された流れ。いまやったら大問題になるけど、当時の状況をふまえたら「盗掘」にはあたらへんで、ということになるねん。
※サカイタイムズでは堺市民にわかりやすいよう堺弁で書いています。 堺弁β版について