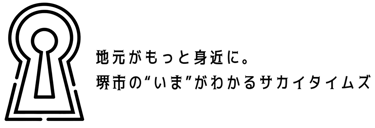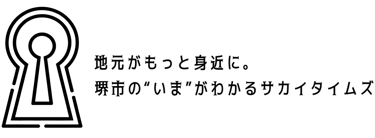堺市の里親制度の現状と課題
堺市で親や親族と暮らせない子どもは305人 里親登録はわずか87家庭
堺のニュースインタビュー・特集


里親制度とは?
こども家庭庁によると、日本にはさまざまな事情で親や親族と暮らせない子どもがおよそ4万2千人いる。そうした子どもを家庭に迎え入れ、愛情と理解をもって育てる仕組みが「里親制度」だ。堺市で里親支援を実施している子ども家庭支援センター清心寮リーフ(以下、リーフ)の山野さんは「堺市では本当に養育里親の数が足りず、困っています」と話す。
里親の役割と養子縁組との違い
里親は法律上の親子になる養子縁組とは異なり、一定期間、子どもを家庭に迎え入れて養育する制度。期間は子どもが家庭に戻るまで、あるいは自立するまでとさまざま。親子になるわけではないが、子どもが信頼できる大人と関係を築くことを重視している。
堺市には305人
リーフのまとめによると、堺市では令和6年度末時点で親や親族と暮らせない子どもが305人。そのうち里親家庭で育っているのは68人、全体の22.3%にとどまる。残る8割近くは乳児院や児童養護施設で生活。里親家庭にいる68人も短期や週末のみの委託を含んでおり、必ずしも長期の生活とは限らない。
里親の登録と現状
堺市で養育里親として登録している家庭は87。しかし実際に子どもを受け入れているのは43家庭にとどまっている。施設で暮らす子どもは305人に上るため、登録者数は明らかに不足しているのだ。養育里親は圧倒的に分母が少ないのが現状だろう。もちろん、里親登録までには研修や審査など複数の過程を経る必要があるが、その準備期間は、施設で育つ子どもたちの時間と比べれば短いといえる。
里親への国民意識
里親登録をためらう理由の一つとして、経済的な不安がある。日本財団が行ったアンケート調査によると、里親になっていない人のうち約4割が経済面を不安視していた。ところが調査対象者に、里親には手当や生活費の支給があること、短期の里親制度もあることなどを伝えたところ、里親になる意向を示す人は6.3%から推計12.1%にまで増える可能性があることが分かった。制度の存在や支援内容を知ることが、担い手を増やす大きな鍵になるといえる。
経済的な支援
里親には国から手当や生活費が支給される仕組みがあることはあまり知られていない。金銭目的になってしまわないための措置でもあるが、養育里親の場合、1人あたり月額9万円の里親手当と、子どもの生活費として乳児以外で約5万7千円/月、乳児で約6万6千円/月が支給される(こども家庭庁HP)。さらに教育費や医療費、防災対策費なども補助され、医療費は基本的に公費でまかなわれる。制度を知らない市民も多いが、経済的な支援は里親を支える重要な柱となっている。
里親制度を知るために
リーフの山野さんは、里親制度を理解するうえで押さえておくべき点として次の3点を挙げている。
里親は養子縁組里親だけではなく、一定期間または自立まで育てる養育里親がある。1週間から2か月程度の短期養育里親もある。
実子がいても、共働きでも里親になることができる。
里親だけで子育てするのではなく、行政や支援機関などさまざまなサポートがある。
堺市で親や親族と暮らせない子どもは305人。そのうち里親家庭で育つのはわずか68人だ。数字の差が示すのは、制度を知る人の少なさと担い手不足の現実だろう。市民にとって身近な課題として理解が広がることが求められている。(笹野 大輔)
10月の里親月間イベント記事はこちら:10月は里親月間 堺市各地でシンポジウムやパネル展